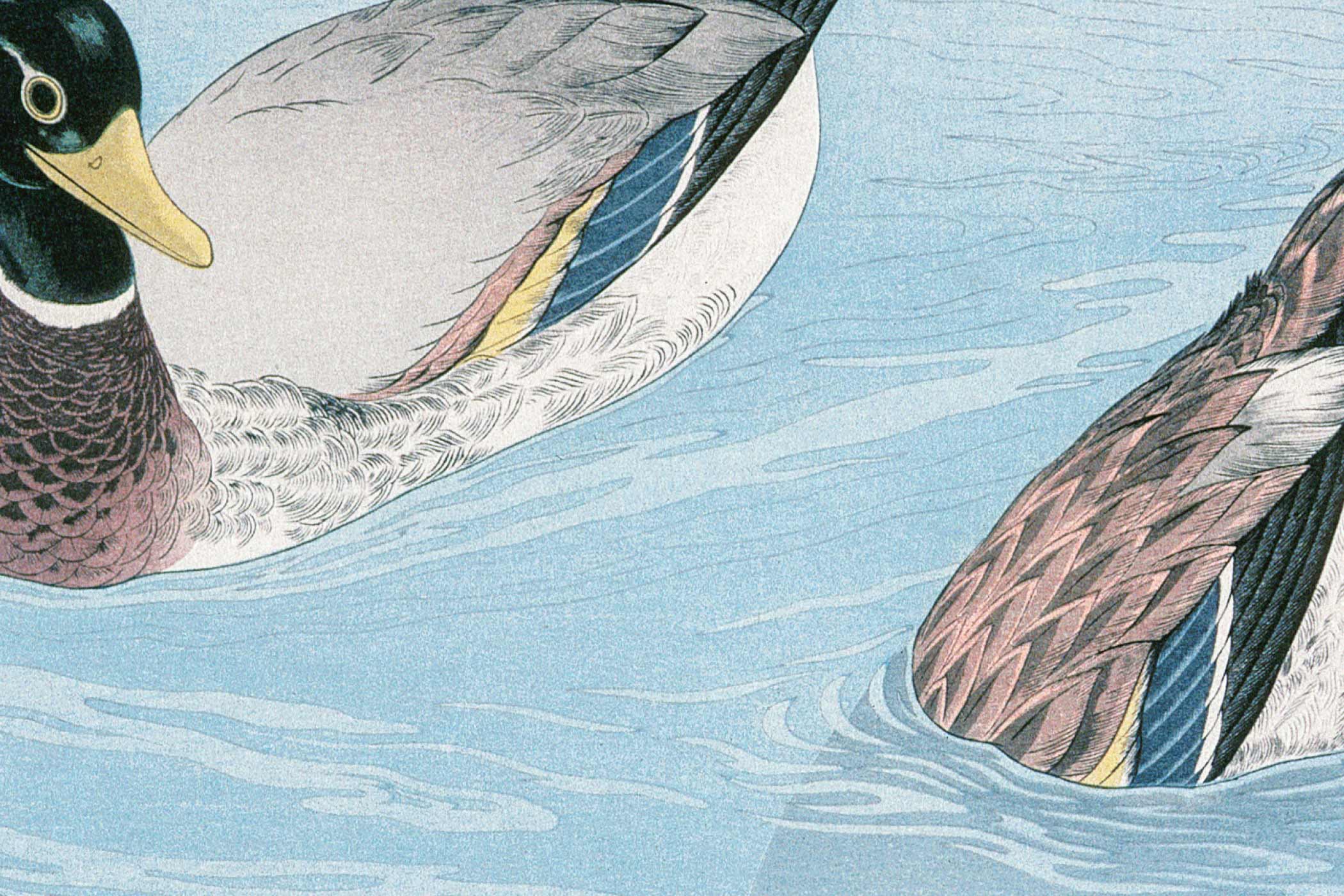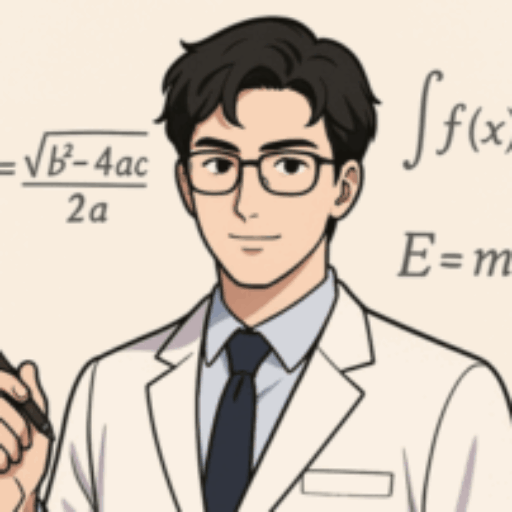買い物中、「今だけ50%OFF!」という文字を見ると、つい財布のひもがゆるんでしまう――そんな経験、誰にでもありますよね。
でも本当にそのセール、おトクなんでしょうか?
実は、多くの「お得そうな」表示には、数学的に見るとカラクリがあるのです。
■ 実体験:思わず買った“半額”の服

ある日、ショッピングモールで「全品半額!」のポップが目に入りました。
前から気になっていたジャケットが13,000円→6,500円になっていたんです。
「半額なら買うしかない!」と即決。
ところが、後日同じブランドのオンラインストアを見てみると
――そのジャケットの定価は10,000円。
つまり、セール前の値段がそもそも吊り上げられていたんです。
こうしたケース、実は珍しくありません。
一見おトクに見えても、数学的に冷静に考えれば損をしていることが多いんです。
■ 割引の「数字マジック」

セールの割引表示には、いくつかの“数字マジック”が隠れています。たとえば:
| 表示 | 実際の割引率 | 印象の違い |
|---|---|---|
| 20%OFF + 20%OFF | 実際は36%OFF | 40%OFFではない |
| 「2つ買うと3つ目無料」 | 実質33%OFF | 「1つ無料」で強い印象 |
| 「最大70%OFF」 | ほとんどの商品は10〜20% | ごく一部だけ大幅割引 |
特に「◯%OFF+◯%OFF」のトリックは要注意です。
たとえば1万円の商品に「20%OFF+さらに20%OFF」と書いてあっても、
10,000円 → 8,000円(1回目の20%OFF) → 6,400円(2回目の20%OFF)
つまり**実際の割引率は36%なんです。
「40%OFFだ!」と勘違いしてしまう人は多いですが、これも数学的に考えれば一瞬で見抜けます。
■「ポイント還元○%」も冷静に見ると…

最近は「ポイント還元5%」や「PayPayで10%戻ってくる」などもよく見ますね。
でも、ここにも数字の落とし穴があります。
たとえば、1万円の商品を10%還元で買うと、1,000円分のポイントが戻ります。
一見1,000円得したように感じますが――
そのポイントを使うときに制限がある(有効期限や対象外商品など)ことも多いんです。
つまり、「還元=値引き」ではなく、条件つきの割引なんです。
これも「割引率」や「有効活用率」を考えることで、数学的に実質価値を見積もれます。
■ 数学で“真のおトク”を見抜く3つの視点

数学を使えば、見せかけの数字に惑わされず、本当の価値を判断できます。
ポイントは次の3つです。
① 割引率ではなく「支払総額」で比較
たとえば:
- A店:10,000円→30%OFF=7,000円
- B店:8,000円→10%OFF=7,200円
ぱっと見ではAのほうが安そうですが、送料が500円なら…
A店=7,500円、B店=7,200円。
B店のほうが安いですよね。
見かけの割引率ではなく、最終的な支払額を考えるのが数学的な判断です。
② 「×個買うとおトク」は1個あたりの単価で考える
たとえば「2個で500円」と「1個280円」の場合、
2個で買えば1個あたり250円。
こうした単価計算(単位あたりの値段)こそが、数学的節約の基本です。
実際、私はスーパーで「大容量パックがおトク」と思って買ったら、
小さいパックのほうが1gあたり安かったことがあります。
冷静に1g単価を見れば、簡単に判断できるんです。
③ 「時間×お金」の効率も考える
セールに行くために往復1時間かかるなら、その移動コストも無視できません。
もし時給1,000円として、1時間使って500円得しただけなら、実質損です。
これは「機会費用」という考え方で、経済学的にも数学的にも大事な概念。
■ 数字を使うと「損しない自分」になれる

私たちは日々、数字に囲まれています。
しかし「数字に惑わされず、数字で考える」力があるだけで、
生活の質はぐっと上がります。
- 割引率よりも支払総額を見る
- ポイントよりも実際の還元価値を見る
- 「安い」よりもトータルでおトクを考える
これらはすべて、数学の基本的な考え方――比・割合・単位あたりの考えにすぎません。
学校で学んだ算数が、実はそのまま節約スキルになるんです。
■ まとめ:数学は「生活防衛の武器」

「数字に弱い人」ほど、見せかけの広告にだまされやすくなります。
でも数学を味方につければ、冷静にお金を守ることができます。
数字を理解することは、自分をだまさない力でもあるのです。