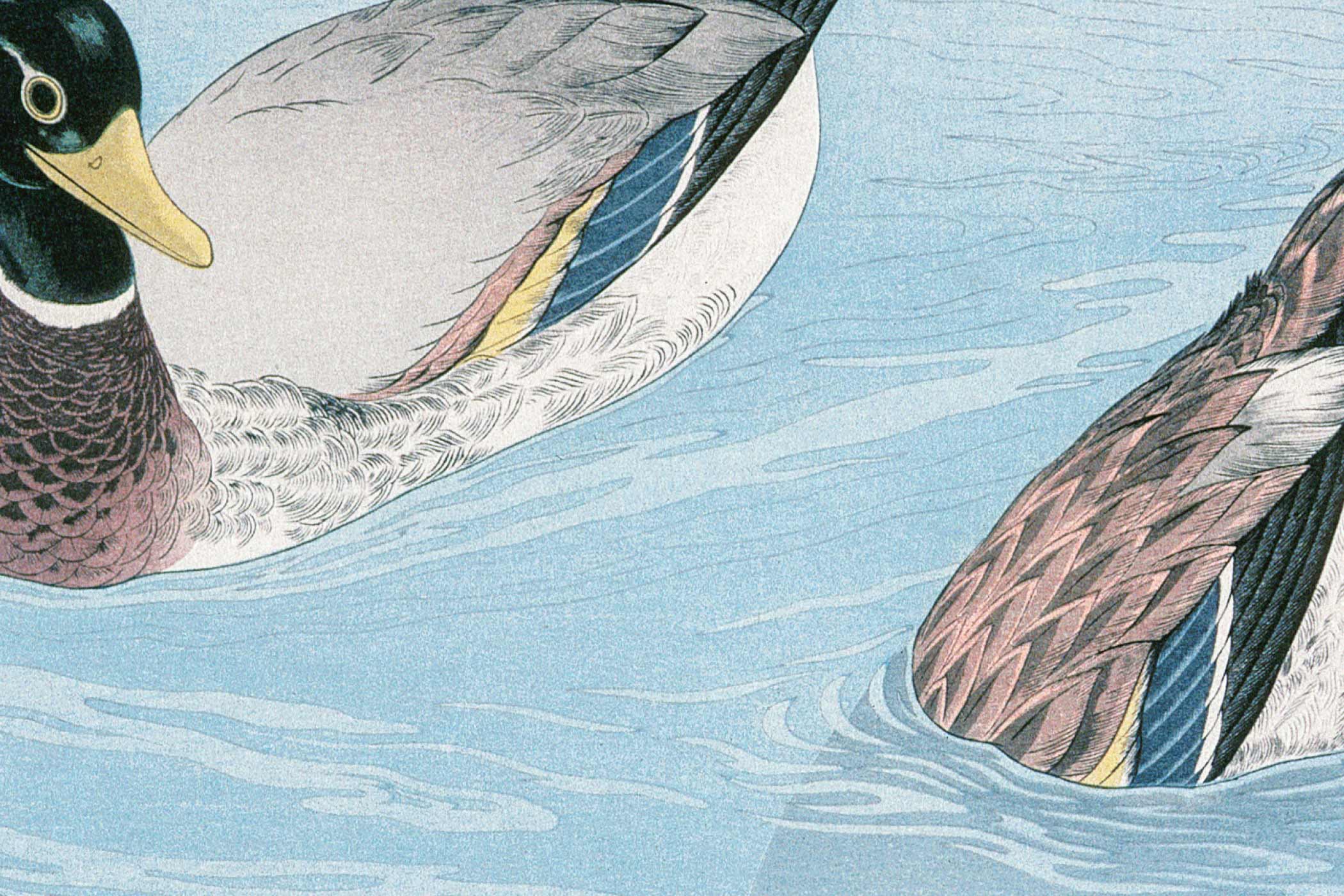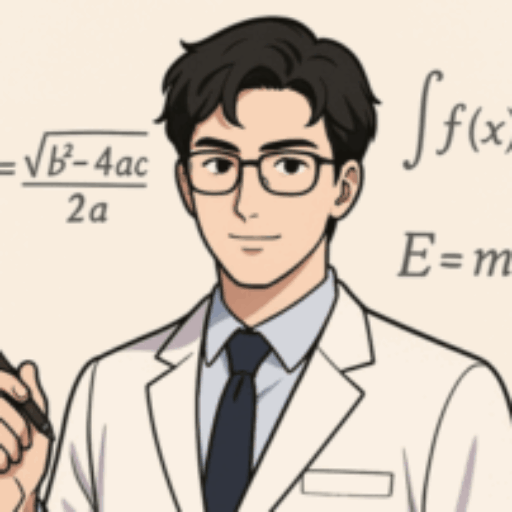Netflix、Amazon Prime、Spotify、スマホゲームの月額課金…。
いまやサブスク(定額サービス)は生活の一部となっています。
しかし、「気づいたら毎月の固定費が増えていた」という経験をした人も多いのではないでしょうか。
私自身も大学時代、気軽に登録したサブスクが積み重なり、月額で1万円以上払っていた時期がありました。
毎回は数百円〜千円程度なので気づきにくいのですが、1年単位で計算すると驚くほど大きな額になります。
ここで役に立つのが数学的な視点です。
サブスクは「1か月あたりいくら」ではなく、「年間コスト」「利用1回あたりの単価」に換算して評価すると、本当に必要なものと不要なものが見えてきます。
1. 年間コストで考える
サブスク料金は月額で提示されるため、心理的に「小さな出費」と感じやすいのですが、これを年間に換算すると実態が見えます。
- Netflix:月額990円 → 年間11,880円
- Spotify:月額980円 → 年間11,760円
- Amazon Prime:月額600円 → 年間7,200円
- スマホゲーム課金(バトルパス等):月額1,200円 → 年間14,400円
合計:年間45,240円
実際、私が大学1年生のときに使っていたサブスクは上記のような内容で、1年に4万5千円近く支払っていました。
これを「月4000円ちょっとだから大丈夫」と思っていたのですが、年間で5万円弱と考えるとかなり重い負担に感じます。
結論:サブスクは必ず「年間コスト」で評価する。
2. 利用1回あたりの単価を計算する
さらに一歩進んで、「利用頻度」で割って考えると、費用対効果が鮮明になります。
例えば、Spotify(月額980円)を週に1回しか使わない人の場合:
- 年間利用回数 = 52回
- 年間コスト = 11,760円
- 1回あたり = 約226円
これなら、必要なときに曲を購入したり、広告付きの無料プランを使った方が安くなる可能性が高いです。
一方、私のケースではNetflixを「週に10時間以上」観ていたので、1時間あたりのコストは 990円 ÷ (40時間/月) ≈ 25円。
これは映画館やDVDレンタルと比べて圧倒的に安く、むしろお得でした。
結論:利用頻度で割り算して「1回あたりの単価」を計算する。
3. サブスクの「期待値」を見極める
サブスクには「いつでも使える」という安心感がありますが、数学的に言えば「実際に使う確率」が低ければ損になります。
例:あるゲームの月額パス(1200円)。
- 特典は「毎日ログインで石がもらえる」。
- 1日あたり40円相当の価値。
- しかし実際のログイン率は50%。
期待値 = 40円 × 0.5 × 30日 = 600円相当。
つまり、1200円払って600円分しか得していない計算になります。
私も実際に「忙しくてログインできず、課金が無駄になった」経験があります。
これをきっかけに、利用頻度が不確実なサブスクには手を出さないようにしました。
4. 固定費の総和を「家計の割合」で見る
もう一つの落とし穴は、「サブスクの合計額が家計に占める割合」です。
- 学生時代の私:収入(月バイト代)= 約6万円
- サブスク合計 = 約1万円
- サブスク率 = 16%
つまり「稼ぎの6分の1がサブスクに消えていた」わけです。
これはかなり危険な状態でした。
社会人になった今は、収入が増えたことで割合は下がりましたが、それでも「手取りの5%以内に抑える」というルールを自分で設けています。
結論:サブスクは「合計額」ではなく「収入に占める割合」で管理する。
5. 実体験から学んだサブスク整理の方法
私が実践した「サブスク整理法」を紹介します。
- 全て書き出す
毎月のサブスクを紙に書き出し、合計額と年間換算額を算出。 - 利用頻度を記録する
1か月間、実際に何回使ったかをメモ。 - 1回あたり単価を計算
利用回数で割り算して「本当に価値があるか」を確認。 - 優先順位をつける
「絶対必要」「あった方がいい」「ほぼ使ってない」に分類。 - ルールを決めて整理
- 年間1万円以上使うのに利用が少ないものは解約。
- 収入の5%以内に抑える。
実際、私はこの方法で「使っていないゲームの課金」と「ほぼ観ない動画配信サービス」を解約し、年間で約2万円の節約に成功しました。
6. 数学的にまとめると
サブスク管理を数学的に整理すると、以下の3ステップになります。
- 年間コストに換算して実態を把握する。
- 利用頻度で割り算して「1回あたり単価」を計算する。
- 期待値や家計の割合で本当に必要か判断する。
この考え方を取り入れると、「なんとなく払い続ける」から「数値で判断して選び取る」へと変わり、無駄が減ります。
おわりに:サブスクを味方につける
サブスクは正しく使えば便利でコスパ抜群のサービスです。
しかし数学的に冷静に分析すると、意外と「使っていないのに払っているもの」が多いことに気づきます。
私自身、サブスクを整理したことで、毎月数千円、年間数万円の節約につながり、そのお金を投資や自己投資に回すことができました。
「月額〇〇円だから大丈夫」と思ったら、一度計算してみてください。
きっと「本当に必要なサブスク」と「いらないサブスク」が見えてくるはずです。