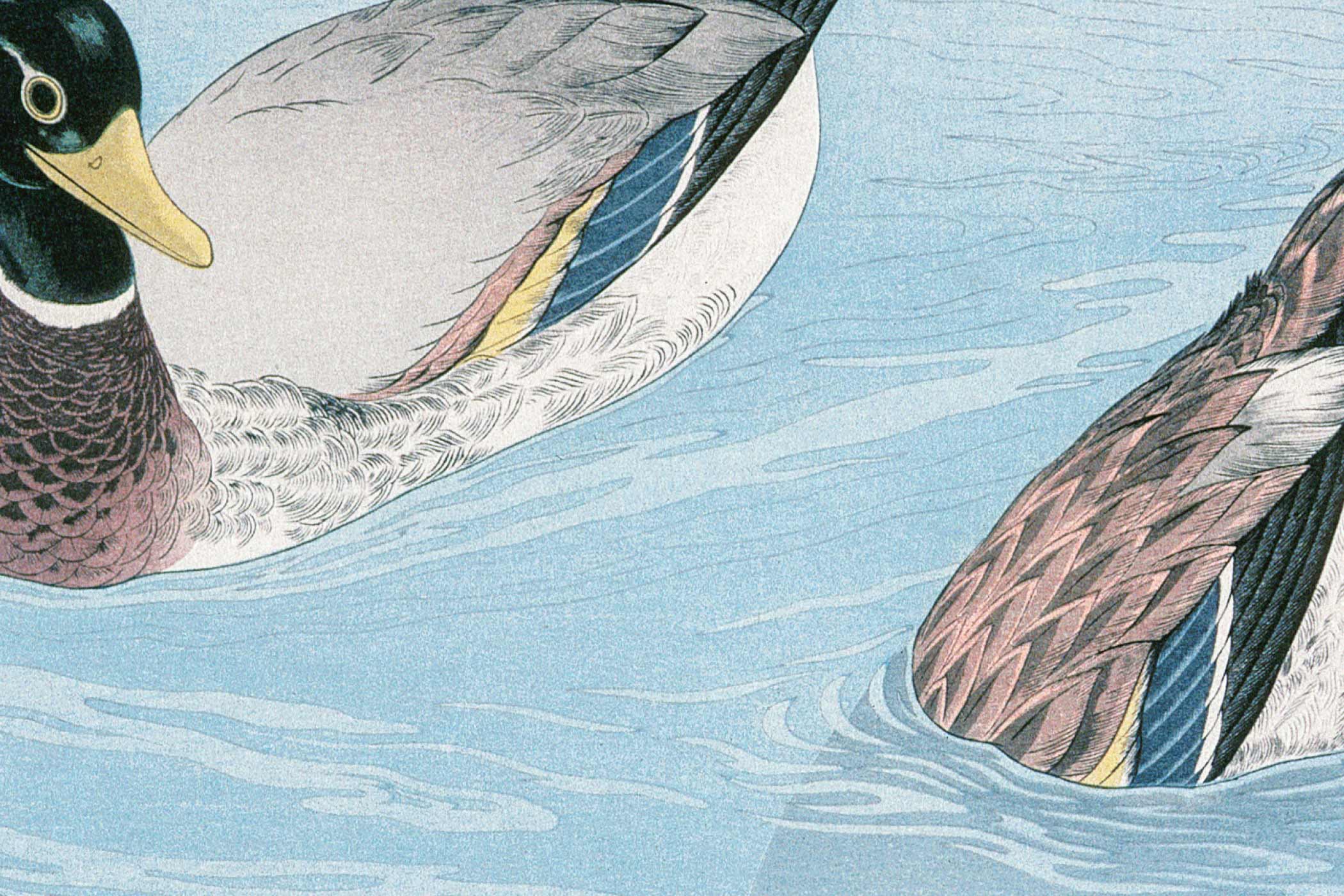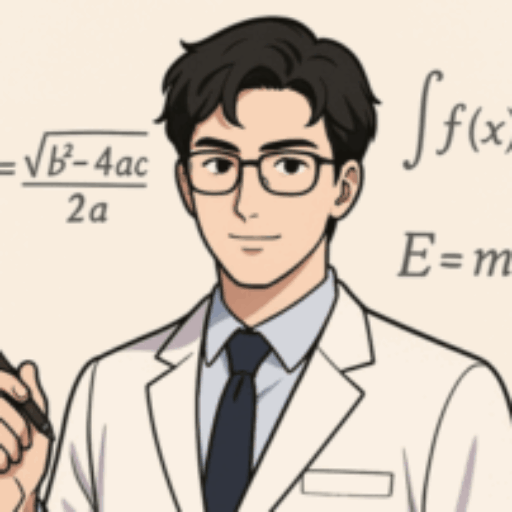「投資を始めたいけど、リスクが怖い」
「NISAや株式投資、仮想通貨の広告をよく見るけど、どれが本当にお得なの?」
こうした疑問を抱く人は多いと思います。
私自身、大学時代に株式投資を始めたとき、最初は感覚で売買してしまい、数万円を失った苦い経験があります。
しかしその後、「数学的な視点」を持ち込むことで投資判断の軸が安定しました。
この記事では、数学を使って投資のリスクとリターンを見える化する方法 をお伝えします。
特に「平均」「中央値」「期待値」「分散」といった統計の基本概念を生活レベルで活用できる形に落とし込みます。
1. 「平均値」だけを信じると危険なワケ
投資信託のパンフレットなどで「年率リターン 5%」と書かれているのを見たことがあるでしょう。
これは単純平均ですが、必ずしも投資家が体感するリターンと一致するわけではありません。
例えば、ある投資商品が2年間で以下の動きをしたとします:
- 1年目:+50%
- 2年目:−40%
単純平均だと: ( 50% + (−40%) ) ÷ 2 = +5%
「平均するとプラスだから良い投資商品だ!」と思いがちですが、実際の資産の動きを追ってみると…
- 初期資産100万円
- 1年目:100万円 × 1.5 = 150万円
- 2年目:150万円 × 0.6 = 90万円
結果は マイナス10万円。
このギャップこそ「平均値を鵜呑みにする危険」です。
2. 「中央値」でリスクを把握する
平均値の落とし穴を補うのが 中央値 です。
中央値は「データを小さい順に並べたときの真ん中の値」で、極端な数字に引っ張られにくい特徴があります。
例えばある投資コミュニティで10人がそれぞれの年間利益を報告したとします:
- +200万円, +150万円, +100万円, +80万円, +60万円, +50万円, +30万円, +10万円, −20万円, −500万円
平均すると: (200+150+100+80+60+50+30+10−20−500)/10=+16万円
「平均すると儲かっている!」という結果ですが、中央値は +55万円。
つまり大半の人は安定して利益を出している一方で、一部の大損が平均値を引き下げていることがわかります。
私自身、仮想通貨で小さな利益を積み重ねていた時期に、ある1回の大きな損失で全体の平均収益がマイナスになったことがありました。
実感として「中央値の方が投資のリアルを反映している」と感じた瞬間でした。
3. 「期待値」で投資戦略を立てる
ギャンブルや投資の基本にあるのが 期待値(Expected Value) です。
期待値とは「長期的に平均するとどのくらいの利益が見込めるか」を数式で表したものです。
例えば、ある株のシナリオを確率付きで想定してみます:
- 上がる(確率0.4):+20%
- 横ばい(確率0.3):0%
- 下がる(確率0.3):−10%
このときの期待値は: 0.4×20+0.3×0+0.3×(−10)=8−3=+5%
つまり長期的には+5%のリターンが見込める商品と判断できます。
私は実際に株のシナリオ分析をノートに書き出し、「期待値がプラスかどうか」で投資判断をするようにしています。
この習慣をつけてから「なんとなくの勘で売買する」ことがなくなり、資産が安定しました。
4. 「分散」でリスクを定量化する
投資におけるリスクは「標準偏差」や「分散」で表すことができます。
同じ平均リターン5%の投資信託でも、
- Aファンド:毎年+5%安定成長
- Bファンド:ある年は+30%、ある年は−20%
両方とも平均リターンは同じですが、Bファンドの方が「振れ幅(リスク)」が大きいです。
私が実際に投資しているインデックスファンドも、同じ株式でも「先進国株」と「新興国株」ではリスク(標準偏差)が倍以上違うことがあります。
数学的にリスクを数値化することで、「どのファンドをどれくらいの割合で持つか」を冷静に考えられるようになりました。
5. 実体験:積立NISAで感じた「数学の安心感」
私は大学3年のときに積立NISAを始めました。
月1万円を全世界株式インデックスファンドに投資し、3年間で約36万円を積み立てました。
その結果は、+約9万円(平均リターン約8%)でした。
もちろん「運が良かった」と言えますが、私が安心できたのは「平均リターンだけでなく、分散や中央値を意識していた」からです。
統計的に長期投資はプラスになる確率が高いと理解していたので、短期の値下がりで不安にならずに済みました。
まとめ
投資を成功させるカギは「感情ではなく数字で判断する」こと。
- 平均値 は参考になるが過信は禁物
- 中央値 で多数派の実感を把握する
- 期待値 を計算して長期的な見通しを立てる
- 分散 でリスクを定量的に評価する
数学を味方につければ、投資は「ギャンブル」から「再現性のある資産運用」へと変わります。