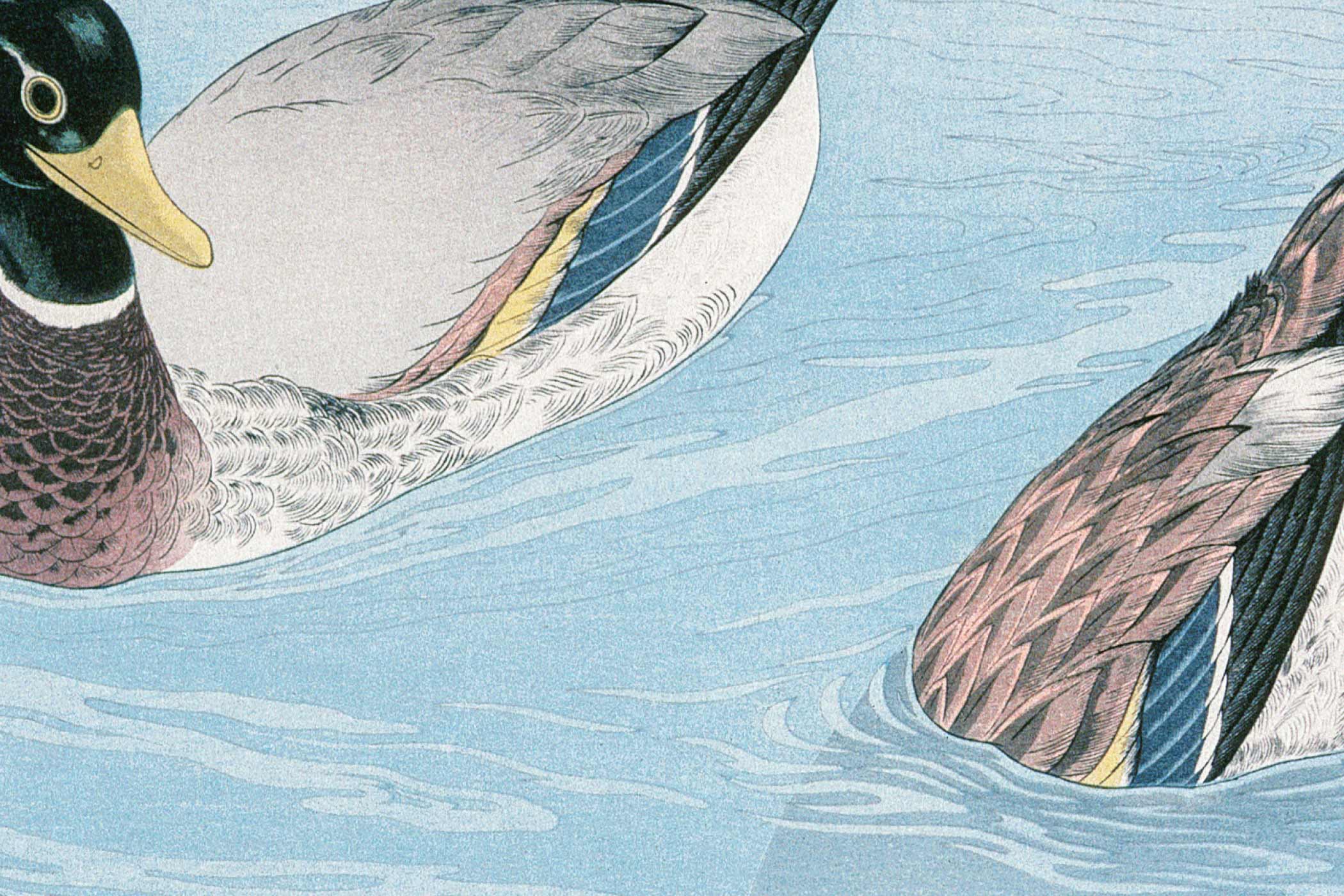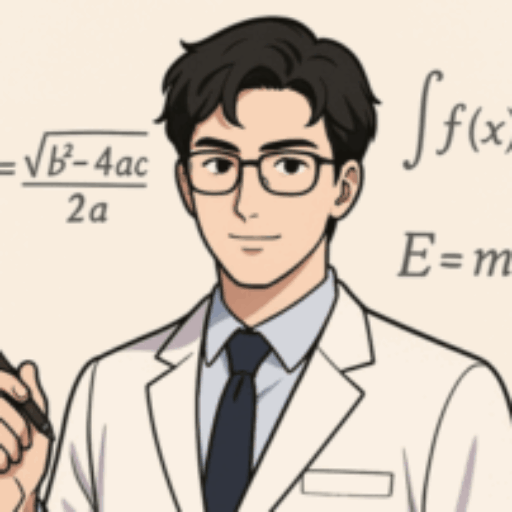「お金の管理」と聞くと、家計簿や節約術、クーポンアプリなどが思い浮かぶかもしれません。
しかし実は、もっとシンプルで強力な武器があります。
それが 数学的な思考 です。
私自身、学生時代から家計をきちんと管理するために「数式」を使って生活の効率を高めてきました。
スーパーでどちらが本当に安いのか、サブスクの契約を続けるべきか、外食か自炊か——こうした判断はすべて数学で「見える化」できます。
この記事では、私が実際に使ってきた 節約につながる数学のテクニック3選 をご紹介します。
節約術①:単価計算で「本当に安い」を見極める
スーパーでよくある「特売セール」。
例えば、すき家の牛丼並盛と大盛の値段差を考えるのと同じで、
単価あたりのコスト を比較しないと損をすることがあります。
・500mlのペットボトルが120円
・2Lのペットボトルが180円
直感的には「500mlの方が買いやすい」ですが、数学的に見ると
500ml×4=2000ml
120円×4=480円
つまり2Lを買う方が 約62%もお得 です。
私はこの「単価比較」を習慣にしただけで、月に2000円近くの節約ができました。
これは年間にすると 24,000円 です。
数学を知っているかどうかで1年の外食1回分以上の差が生まれるのです。
節約術②:サブスクの「期待値」を冷静に考える
動画配信サービスやジムの月額課金は、「本当に使っているか?」を数式で確認する必要があります。
私が実際にNetflixを契約していたときの話です。月額990円。
平均して月に映画を3本観ていました。1本あたり 330円 です。
レンタルショップで借りると400円前後なので「まあお得かな」と思っていました。
ところが、大学の忙しい時期に1か月で1本しか見ないこともありました。その場合
990円÷1=990円
つまりレンタルの方が安いのです。
このとき、私は「自分の利用状況を数理的にモニタリング」して、
利用頻度が少ないときは解約し、再開したくなったら入会し直す方式に切り替えました。
結果、年間で7,000円ほどの節約 につながりました。
節約術③:ポイント還元率を「利回り」で評価する
キャッシュレス決済が普及した今、どのカードやアプリを使うかでリターンが大きく変わります。
例えば、Aカードは 1%還元、Bアプリは 0.5%還元+月に1回使うとクーポン100円。
私の利用金額を月3万円とすると、
・Aカード:3万円 × 1% = 300円分還元
・Bアプリ:3万円 × 0.5% = 150円 + 100円クーポン = 250円分還元
つまり月額ベースではAカードの方が有利ですが、
もしBアプリのクーポンを有効活用できるなら実質は差が縮まります。
私は実際に「どのカードを使ったら1年でいくらリターンか?」をExcelにまとめてみました。
結果、最適化するだけで 年間約12,000円(ほぼ1か月分の電気代) を浮かせられると分かりました。
数学は節約の「武器」になる
・単価計算 → スーパーでの無駄遣いを防げる
・期待値の思考 → サブスクや保険を冷静に判断できる
・利回り比較 → キャッシュレス時代に最適なカードを選べる
私自身の実体験からも、数学を生活に組み込むことで 年間数万円の節約効果 を実感しました。
これは「ちょっとした副収入」と同じです。
「数学=入試科目」というイメージを超えて、
家計を守るための実践的スキルとして数学を活用してみてください。